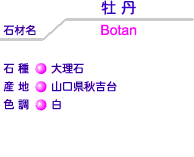 |
 |
 |
|||
| 鍾乳洞で有名な秋吉台付近の美祢市大嶺台、および秋吉台の一角、経塚山から産出する白大理石です。 国産大理石は、その約60%が山口産で占められています。建材のほか美術工芸品、花瓶、灰皿などに利用されます。加工業者は美祢市、秋芳町、美東町に約1OO軒が集中していますが、最近は海外からの安価な輸入材に押され気味です。 |
|||||
| 際立った白さは、まさに優雅「牡丹」の白い花を連想させます。石材名の由来も、そのあたりにありそうです。 「大嶺(おおみね)大理石」「秋吉(あきよし)大理石」と、それぞれ産地名をつけて呼ばれる大理石の一つです。「大理石」の語源は、中国の大理石産地である雲南省の大理府の地名から由来したものです。 ちなみに、大理石は、石灰岩が熱や圧力によって緻密な結晶に変化した石のことですが、建築の世界ではやや幅を拡げ、装飾用に磨くことが出来る硬さの石灰岩や、トラバーチン、オニックス、蛇紋石などもその仲間に含めています。大理石は、変化に富んだ色や柄が魅力で、とりわけいろいろな石が砕けて再び固まった更紗(さらさ)模様は大理石の典型とされています。 |
|||||
| 秋吉台は,山口県のほぼ中央部、美祢市から秋芳町、美東町にかけての地域にある、東西約16km、南北約8km、面積約130平方kmの石灰岩層の台地です。大部分が国定公園に指定された日本一の広さのカルスト台地です。 秋吉台を構成している石灰岩は、古生代末の石炭紀(3憶5千万年前)から二畳紀(2憶5千万年前)にかけて、海中で生物群が堆積して出来たものです。堆積した厚さ1000m以上にもなり、そのため、石灰岩は数多くの化石を含んでいます。この石灰岩は今からおよそ2億年前の中生代のジュラ紀に陸上に姿を現し、その後、何度も大きな地殻の変動を受け、熱や高圧によって再結晶して、方解石の集合体である大理石になりました。 こうしてできた秋芳町の大理石は、日本の埋蔵量の70%を占め、地場産業の大理石加工業を発展させ、観光土産品や建築板材として広く使われています。 |
|||||